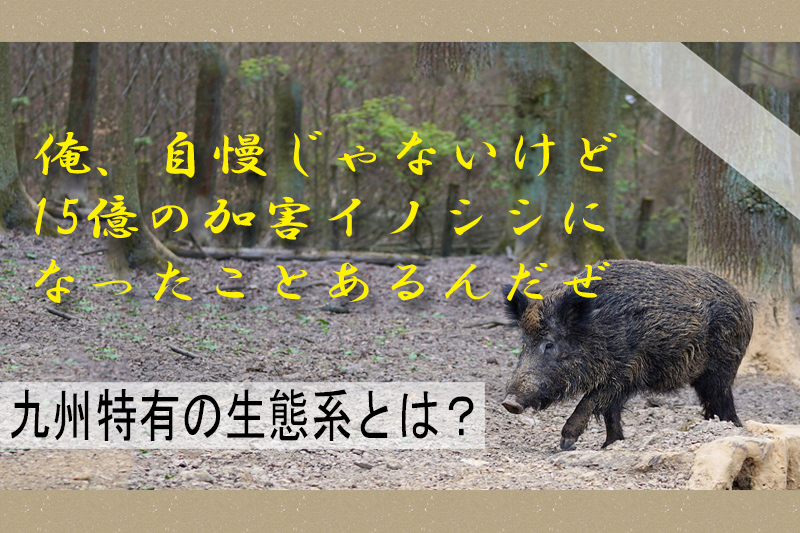九州に特徴的な生態系を紹介しながら、その動物たちが及ぼす被害事例や実際に行われている主な対策を紹介します。
九州地方特有の生態系
地理と気候
- 九州・沖縄地方は日本列島の南西に位置し、日本海、東シナ海、太平洋に囲まれた地域
- 気候は本州と比べると少し温かく、夏から秋にかけて台風が直撃しやすい
- 南北約1200kmに及んで亜熱帯・暖温帯・冷温帯の森林が連なる地域でもあり、世界でも珍しい地域
生態系において最も特徴的なこと
- クマがいない
- 対馬や奄美大島、沖縄本島、西表島など独特の生態系を持つ島がいくつも存在している
1つ目:クマについて
本来は九州地方にも生息していたツキノワグマは、ごく最近までは環境省のレッドリストに「絶滅の恐れがある地域個体群」として掲載されていた。
しかし、ここ数年明確な目撃情報や証拠がないため、2012年にすでに絶滅してしまったとして絶滅危惧のリストから除外されることとなりました。

その後も多くの専門家や写真家が九州で生存しているツキノワグマを探し続けていますが、あくまでクマである”可能性が高い”情報を得られただけで、確実な証拠は未だに得られていません。
九州のクマについて興味深い点は、ここ数年で急激に生息頭数が減ったというわけではなく、昭和初期にはすでに九州に生息するツキノワグマはほとんどいなかったということです。
生息しているクマも、大分県・宮崎県・熊本県の県境にあたる祖母・傾山山系の一部地域にのみ生息する状況でした。

2つ目:独特の生態系を持つ島の存在について
対馬・奄美大島・沖縄本島・西表島・屋久島などが挙げられます。
各島にはその島独特の固有種(その島にしかいない動物)が存在しています。
| 島名 | 主な固有種(例) |
|---|---|
| 対馬 | ツシマヤマネコ、ツシマテン |
| 奄美大島 | アマミノクロウサギ、アマミヤマシギ |
| 沖縄本島 | ヤンバルクイナ、ノグチゲラ、ヤマガラなど |
| 西表島 | 多様な熱帯動植物 |
| 屋久島 | 世界自然遺産に登録、豊かな森林と生態系 |

 これらの種は、生息地が島内のみという限られた場所である上に、生息数がそこまで多くないため、現地の環境保護施設や保護センターなどでも積極的に保護活動が行われています。
これらの種は、生息地が島内のみという限られた場所である上に、生息数がそこまで多くないため、現地の環境保護施設や保護センターなどでも積極的に保護活動が行われています。
シカによる深刻な被害
獣害被害として多くの被害を出している九州地方のシカについてもご紹介します。
九州地方に限らず、日本列島では過去30年間に シカの生息頭数が大幅に増加しており、それに伴いシカの生息域も拡大し続けています。
シカを取り巻くこの状況は、海を挟んだ九州地方でも同様で、特にシカの食害による生態系の変化は深刻です。
実際にシカの食害によって絶滅した植物や破壊された森林もあり、それに伴う昆虫や鳥類の減少も見られます。
これらのシカ被害は林業を窮地に追い込む勢いで拡大しており、現場は緊急の対応を要しています。
シカによる人への被害
一方で、自然環境のバランス・植物へのダメージ以外に人への被害も懸念されています。
本来は山奥や沢に生息するヒルが、シカに付着して田畑や里山に移動し、人がヒルに吸血されるという被害も確認されています。
獣害被害の特徴
農作物被害に限っては、九州地方ではイノシシ被害が最多!!
- 平成27年(2015年)時点での被害額は約15億円。
- 九州全体の農作物被害の約50%がイノシシによるもの。
- 特に長崎県では8割以上がイノシシ被害。
 効果的な対策によって数年前と比べて徐々に減少はしているものの、今まで育ててきた農作物をこれから収穫しようという収穫期に鳥獣被害を受けることは、金額で計れる実被害だけでなく、農業を運営する意欲の低下や耕作放棄地の増加の原因にもなっています。
効果的な対策によって数年前と比べて徐々に減少はしているものの、今まで育ててきた農作物をこれから収穫しようという収穫期に鳥獣被害を受けることは、金額で計れる実被害だけでなく、農業を運営する意欲の低下や耕作放棄地の増加の原因にもなっています。
特に農業の高齢化が進む過疎地域や比較的規模の小さい市町村では、”農業”という人の食を支える大切な産業自体に大きな影響を与えているのです。
九州の鳥獣別被害額(平成27年)
| 動物種 | 被害額(億円) | 備考 |
|---|---|---|
| イノシシ | 15億円 | 全体の約50% |
| 鳥類 | 6億3000万円 | 福岡県では約35%が鳥類被害(カラスなど) |
| シカ | 4億5000万円 | 宮崎・鹿児島では全体の2〜3割がシカ被害 |
| サル | 1億3000万円 | 局地的な被害 |
※ ただし、都道府県によって害獣となる動物種の割合は異なります。
たとえば・・・
- 長崎県では被害額の8割以上がイノシシ被害であることに対し、宮崎県や鹿児島県では被害額のうちイノシシが占める割合は4割程度で、2〜3割はシカによる被害であること
- 九州の中でも比較的人口や経済面の規模が大きい福岡県では、全体の3.5割ほどがカラスを含めた鳥類による被害であること

九州中南部におけるシカの影響
九州の中南部では、シカの生息数の増大や生息域の拡大が進んでいます。
それに伴い、以下のような問題が起きています。
- 農林業に大きな被害(農作物の食害、苗木や草木の消失)
- 希少植物の減少や絶滅、生態系のバランス崩壊
- 昆虫や鳥類の生息地も失われる深刻な状況
九州・沖縄の森林について:対策と管理
九州森林管理局が一部の森林の管理をしており、次のような対策を行っています。
- 九州森林管理局が調査・管理を実施
- シカによる被害状況・生息地・分布・行動の調査
- 植生保護柵の設置、効果的な捕獲などの対策実施
生息数の推移と問題点
- 1978年~2003年の25年間で、シカの個体数が1.5倍以上に増加
- 九州全域で 約27万頭(適正数約3.6万頭の7倍以上)
この数値は、適正値である3.6万頭の7倍以上の数値です。
ただし、森林被害はシカだけではない様々な要因が絡み合って表面化しつつある被害でもあるのです。
たとえばこのような要因です
- 人による森林の手入れ不足
- 外来種の侵入
- 地球全体の温暖化
主な獣害対策
このような特徴ある九州地方の生態系の中で、獣害被害の対策はどのように行っていけば良いのでしょうか。
ここでは、実際に九州地方で実施されている獣害対策を2つ紹介します。
1つ目:シカの生息地拡大を防ぐ対策について
シカによる獣害被害が最も多い霧島・熊本南部・宮崎北部では、県や市町村、猟友会の協力を得てシカ対策検討会議が実施され、広域移動規制策柵(シカ・ウォール)の設置が検討されました。
広域移動規制策柵(シカ・ウォール)とは、徐々に生息地を拡大しているシカが これ以上生息地を広げないための対策で、現時点でシカが生息していない地域に入る前に柵を設置するというものです。
実際にこの対策は、様々な機関との協力を得て実地され、長さ2.5kmにも及ぶ柵を設置することとなりました。
2つ目:熊本県あさぎり町という中山間地区での獣害被害対策
この地域では、かつて作物を全く収穫できないほど深刻だった獣害被害を、専門家の指導と全住民の協力によって撲滅したのです。
その結果・・・
放置されていた果樹園の再生や特産品の販路拡大など、農業だけでなく地域全体にも潤いを取り戻した獣害被害対策の成功例とも言える取り組みです。
取り組みの具体的な内容
- 専門家による集落の地理的環境を考慮した最適な侵入防止柵の検討
- 設置、管理されていない果樹の除去、藪や雑木林の整備
このように 専門家による適切な指導を取り入れ、集落全体が一つになって取り組んだことによって被害を撲滅することができたということで、中山間地域集落における獣害対策のモデルとして評価され、平成27年度鳥獣被害対策優良活動表彰では農林水産大臣賞を受賞しています。