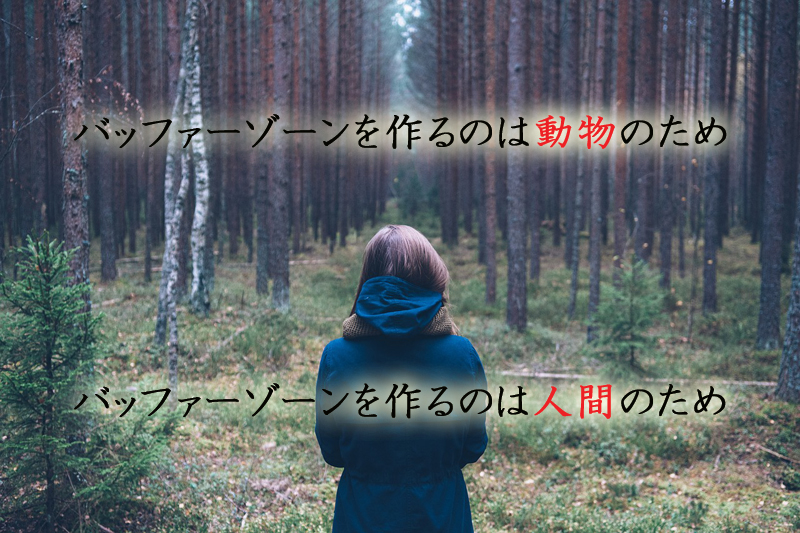獣害対策として柵やフェンスの使用を検討している方に向けて、バッファーゾーンの重要性と効果、効果のある害獣などをご紹介します。
バッファーゾーンとは?
バッファーゾーンとは人の生活圏と野生動物の生活圏を隔てる緩衝地帯のことで、人間の気配や存在を感じさせることで、そのエリアから先に侵入させづらくする効果があります。
田畑や集落への侵入を防止したい場合、物理的な侵入防止として柵やフェンスの設置が検討されることが多いですが、バッファーゾーンを作り出すことの効果も大変大きく、被害状況や周辺環境によっては柵やフェンスを設置しなくても被害が激減する可能性があります。
具体的には、田畑や柵の周りに生えている草木や茂みの刈り払いを行って周辺の見通しを良くし、動物たちが身を隠す場所を無くしてしまうのです。バッファーゾーンには、田畑に近い草むらや近隣の耕作放棄地を利用することが多く、効果を維持させるためには年に数回の定期的な刈り払いと環境整備が必要になります。
バッファーゾーンの設置は、草陰を好むイノシシに特に効果があり、草原や平地にも姿を表すシカには効果が少ないこともあります。その他にも、タヌキやアライグマなどの中型獣にも効果があります。
メリット・デメリット
バッファーゾーン設置における最大のメリットは、田畑および人の生活圏への侵入抑制と柵類の効果向上です。これらの効果があることで、結果的に動物と車の衝突事故や柵類の故障も劇的に減少します。ここからは柵の種類によるバッファーゾーン設置の相性をご紹介します。
まず、ネット柵や電気柵など強度が弱い柵類を設置している地域では、バッファーゾーンの設置が特に効果的です。ネット柵は、デメリットとしてツルやツタが絡まることで重みが増してネットが取れてしまう、近くに茂みがあることで動物が近づきやすくなりネットを噛みちぎられてしまうなどの事例が珍しくありません。
電気柵についても同様で、強度の点はもちろんのこと、草木が電気柵に触れてしまうことで流れる電気が弱くなってしまい、動物への電気ショックが効かなくなる場合もあります。これは強度が弱い電気柵にとっては致命傷で、電気が通っていなければただの簡易的な電線柵となってしまい、柵ごと倒されたり隙間をくぐって田畑に入られたりする可能性が高まってしまいます。
一方、金属柵やワイヤーメッシュ柵などは、ネット柵や電気柵と比べて強度はあるものの、全く管理をせずにそのまま放置していると劣化や倒木・土砂による破壊の可能性も考えられます。動物たちはこのような隙間を狙って侵入してくる可能性があるため、バッファーゾーンを作ることで将来的な修繕費を削減することにもつながります。
バッファーゾーン設置のデメリットとしては、定期的な環境整備がありますが、これらの手間で防げる被害や削減できる対策費がありますので、正しい整備方法を知った上で継続的に整備を行いましょう。バッファーゾーンの整備については、季節や周辺環境によってやるべきことが変わってきますので、次の項目で詳しくご説明します。
バッファーゾーンの整備
バッファーゾーンの整備は、年に2〜4回を目安に定期的に行いましょう。
整備の内容は、周辺環境として下草の刈り払いやツル・ツタの除去、忌避剤の散布などがあり、農業従事者が自らの田畑の周りを整備することもあれば、周辺地区の住民や農家の方が合同で整備を行う場合もあります。具体的な対策は周辺の立地や環境に応じて異なるため、画一的なマニュアルがあるわけではありませんが、一般的には春から夏にかけて下草を刈り払い、秋には落葉樹の落葉を除去・処分することが多いです。
また、大型の台風や大雨などの自然災害で、柵に被害が及びこともあります。例え集落や都心の被害はなくても、山林では小規模の土砂崩れが起きていたり、雷で木が倒れていたりする可能性もあります。大雨・強風による土砂崩れ・倒木は、雨風が止んだ数日後に発生する可能性もありますので、点検をする際は、必ず周囲の安全、身の安全に十分注意し、雨風が収まって数日後あけて複数人で点検を行うようにしましょう。
近年では、バッファーゾーンの整備を簡易化するために耕作放棄地や田畑の周辺に家畜を放牧する取り組みも行われています。
日本では農地法という法律のため、農業用地を農業以外の目的で使用することが原則禁止されています。しかし、畜産業であればこの農地法による問題はありません。近年畜産業で懸念されている問題として、畜舎で生活する家畜の動物福祉や肉牛の肉質向上、家畜育成の低コスト化などがあるため、この耕作放棄地での放牧による農地の活用は、農業にも畜産業にも利点のある土地活用として注目されつつあります。